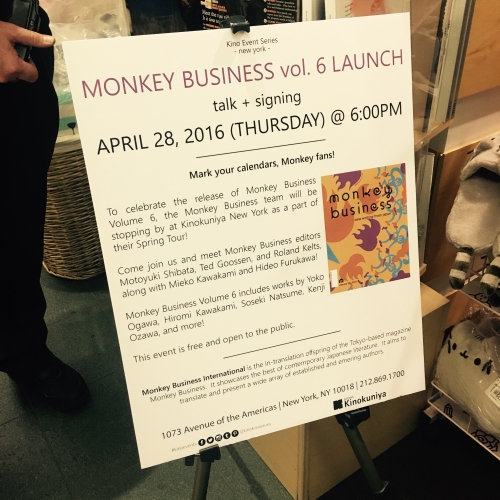10年前に、吉田アミさんと開催したイベントのゲストに来ていただいたのが雨宮さんとの出会い。当時わたしは音楽をやっていて、詩を書いていたけれどまだ小説は書いていなくて、30歳になるかならないかの頃だった。
薄暗い会場で誰が誰かわからないのに、客席の後ろのほうでまあるく浮かびあがるきれいな女の人がいた。座席って暗いし、当日も長丁場だったし、みんなそれぞれリラックスできる姿勢でゆるゆると座っているものだけど、黒い服を着てショートボブの髪型をしたその女の人はひとりだけ異様なほどに背筋がぴんと伸びていて、ほんとうにぴくりとも動かないで、まっすぐ舞台のほうを見つめていた。それが今でも目に焼きついている。登壇されたあとで、それが雨宮さんだとわかった。
それから、ときどきメールをするようになって、たまに電話をするようになった。当時も今も、わたしには電話して話をするような友だちがほとんどいないから、最初に電話でしゃべったときの雨宮さんの声をよく覚えてる。そのとき座ってて今はもうないソファの柄なんかもはっきり覚えてる。
最初はなんだったっけ。そうだ、小説が新人賞を授賞してばたばたとしている時期で、某男性週刊誌からすごく失礼な取材の依頼がきたことがあったんだった。でも、わたしはその雑誌がどういう雑誌か知らなくて、それで雨宮さんに電話して教えてもらったんだった。雨宮さんは「**かあ。微妙だねえ。受けなくてもいいような気がするなあ」と笑って、それからヴォネガットの話とか、ペン回しの動画の話とかしたんだった。あれはなんであんなにどきどきするんだろうね、みたいな話。
そんなふうに、「髪型、ツーブロックにしました」とか、「出産して生活が変わりすぎて白目」みたいなメールや電話はほんのたまにするけれど、じゃあわたしは雨宮さんの友だちだったのかというと、なんて言うのが正しいのかわからなくなる。
おなじ歳で、本を贈りあったり、時々ラインをしたりするけれど、わたしは雨宮さんの個人的なことは何も知らないし、ふたりでお酒を飲みにいったこともないし、考えてみれば数えるほどしか会ったことがない。でも、わたしは雨宮さんの本を読んでいたし、ウェブの連載を読んでいたし、インスタグラムで写真を見ていたし、雨宮さん本人にふれている時間よりそっちの時間のほうが多くて、だから、読者だったというのがやっぱり正しいんじゃないかという気がしてしまう。
物を書いている人同士の付き合いには、ちょっとした緊張感と難しさがあると思う。
それは、どうしても、その人との純粋な関係の前に、というか、あいだに、作品(その人の書いている言葉)が存在してしまうから。
「作品と人、どっちが重要か」とか、そういう話じゃなくて、なぜか自然に、作品が先にあってしまうようになる。「書いている物がその人」みたいになってくるところがある。だから、その人にとってつまらない本を書けば、自分はその人にとってつまらない人になるような気がするし、駄作を書けば、その人にとって自分が駄目な人であるような気がする。
これはある意味でまっとうなことで、どんなかたちであれ物を書いて署名して世に問うってことは、それがどんなに仲のいい人からでも、気心の知れた人からでも、つねに厳しく判断されるのは当然のことだからだ。そうすると、お互いの作品を読んで、さらに会って、なんてことは、そのつどにすごいパワーと緊張を強いられることになるから(物書き同士が会えば、作品の話は避けられない)、だんだん会えなくなっていく。日々の忙しさのうえにそのプレッシャーが加わって、自然に距離ができていってしまう。だから、それがどんなに好きな人であっても、仲良くしたいなとふと思ってしまう人でも、文章を書いて生きている人に、友だちとは言っては(思っては)いけないんじゃないかとそんなふうに感じてしまうところがある。最初はわたしも混同することがあったけれど、それは正しくないんじゃないかと思うようになった。だから、小説を書きはじめてからできた小説家の友だちというものがわたしにはいないし、知り合いという程度の間柄じゃないと、作品にたいしてフェアではいられないような気持ちがあるから、仕事以外では誰にも会わなくなっていく。
でも、逆のことも起こる。物を書いている人であれば、その人が書いている物を読んでいることが、なんだか、会うことや話すこと以上に重要な行為になっていくような感覚もしてくるのだ。
だから、雨宮さんと会ってなくても、雨宮さんの連載をリアルタイムで読んでいると(雨宮さんの書くものがおそらくは雨宮さんの実感に多く拠るものだからかもしれないけれど)、雨宮さんに会ったり話したりする以上の濃さで、何かが、そこにあるような気がした。大勢の人に向けて書かれたフィクションにふれているだけなのに、どんどん好きになってしまう。彼女が今考えていることとか、感じていることとかを知ることができているような、そんなような、一方的な、実感がありました(それは同時に錯覚でもあるんだろうけれど)。
そんなふうな仕方でだけど、わたしが知ることのできた雨宮さんという人は、気遣いの人でした。なんてことない数行のメールから、会話のひとことからにじみ出ていました。
「大変だよね、しんどくないですか」みたいなことをさりげなくきいてくれて、自分もしんどいだろうに、すごく気を遣ってくれる人。
そして、とても聡明な人でした。うっかりすると、いつまでも、何でも話して聴いてほしくなってしまうような不思議なちからと、優しさを持った人。
礼儀正しい人でした。相手がどう感じるかを察する人、そしてフェアな人でした。自分が傷ついてきた色々なことを人には味わわせないように、慎重に言葉を選ぶ人。
いつだったか、わたしの作品がかかわった舞台を見に行ってくれて、その感想を電話できいたらあんまりよくなかったみたいで、わたしはしゅんとしてしまったけれど、でも正直で、あと、それから、ときどきネットのやりとりでみせる気の荒いところも好きだった。真面目で。読者のことを本当に大切に思っていて。情が深いけど、押しつけがなくて。「穴の底でお待ちしてます」なんて、あれはもう本当にすごかった。毎回ため息をつくほど見事で、あんな回答は誰にもできない。
読者のみなさんが、彼女の文章から受け取ってきたものを、わたしも読者としていつも受け取っていました。技術も感情も総出で、雨宮さんは書いていたよね。それが何かなのかはわからないけれど、彼女はいつも、彼女が惹かれて振り回されてどうしようもなくて、それでも抗えない強い何かに、尽くしているようにみえました。
初夏に、『おめかしの引力』という本の書評をしてくれて、すごくうれしくて、ありがとうって連絡しようと思ったんだけれど、書評は仕事なんだし、そんなふうに個人的にお礼を言うのはかえって失礼なんじゃないかと思って結局、そのことを言えないままでした。
それから、今月のファッション雑誌に雨宮さんが載っていて、赤いドレスを着ていて、それがすごく素敵でそのことを伝えようと思っていたのだけれど、じつはわたしが企画している別の仕事で正式にお願いをしようと思っていたときだったから、そのまえにそういうメールを出すのは失礼じゃないかと思って、そのことも結局、伝えられないままでした。

これは、『ヘヴン』という小説を書き終わったときに、雨宮さんがくれた石。
わたしはすごくうれしくて、届いたその日から、引っ越ししても、ベッドが変わっても、ずっと枕元においてある石。フランスで見つけてくれたんだって。素敵だよね。つるつるしていて、すごくかわいい。数ヶ月前、なにかのメールの返事に、ずっと伝えたかったそのことを「そういえば雨宮さんがくれた石、大事にしてますよ」とあんまり重たくならないような感じで書いた。書いてよかった。
わたしにとって雨宮さんの文章は、わたしが初めて見た、あの薄暗い客席のなかで浮かびあがる雨宮さんの印象そのものです。
きりりとしていて、目がそらせなくて、一生懸命で、強くて、でも臆病で、すごく緊張していて、まっすぐ。それから、雨宮まみっていう名前がすごく好きです。暖かいのや冷たいのや、しとしとのや激しいのや、明るい日に悲しい日に、いろんな雨が感情みたいにいつもいつまでも、降っている場所。
まだまだ、雨宮さんの文章をたくさん、いつまでも読めると思ってた。どうか、安らかに。